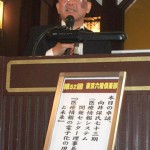まず、最初にMEDIS-DCの紹介をさせていただきますと、1974年に当時の厚生省と通産省によって設立されました財団法人で、現在は、主として、 1) 医療情報に係わる用語やコードの標準化、2) 医療情報の安全な交換や保存に係わる技術の開発、の二つの事業に取組んでおります。

 さて、医療情報のIT化ですが、進展の段階を大きく分類しますと、 さて、医療情報のIT化ですが、進展の段階を大きく分類しますと、
1) 医事会計、オーダリング、各診療部門のシステム、あるいは、それらを統合した病院内でのシステム
2) 病院間や病院と診療所とを連携した地域医療圏内でのシステム
3) 日本全国や生涯に亘って展開したシステム
の三つの段階があります。
第一段階の現状ですが、病床数400床以上の大きな病院では、殆どの病院にオーダリングシステムや電子カルテシステムが導入されています。 一方、中小規模の病院や診療所では、一部で、簡便な電子カルテシステムを導入し、患者さんへの説明や業務の改善、フィルムレス化などに力を発揮してはいま すが、導入の比率はまだまだ低く、中小規模の病院や診療所へのITの導入が大きな課題となっています。
▼情報化の状況(まとめ)
|
診療所 |
一般病院 |
病院
400床未満 |
病院
400床以上 |
| レセプトのコンピュータ処理 |
66.1% |
ー |
ー |
ー |
| レセプト電算処理 |
13.4% |
34.2% |
ー |
ー |
| オーダリング |
ー |
23.7% |
18.8% |
72.9% |
電子カルテ
(予定含む) |
6.3%
(9.9%) |
5.6%
(18.5%) |
4.4%
(21.2%) |
17.9%
(53.1%) |
システムの形態では、医事会計、レセプト処理やオーダリングは、業務の効率化など導入による効果が把握しやすいのに対して、電子カルテは導入による効果が 見え難いと云われています。 電子カルテの導入によるメリットとしては、診療情報を医師、看護師などが共有し、必要なチーム医療が推進されること、患者に対して診療や処置内容を判りや すく説明することに役立つ、などがあり、特に大きな病院ではこのメリットが強く出るようです。 一方、中小の病院では、オーダリングシステムの導入を検討している病院が増しつつありますが、電子カルテのシステムはシステムが高額であること、導入に伴 う効果が明確でないこと、また、診療報酬や税制の措置がないこと、などにより導入に躊躇する病院が多いようです。
 第二段階の地域医療圏内の病院間や病院と診療所との連携に際してのITの利用ですが、遠隔診断(画像診断・病理診断)、患者紹介、診療情報の共有の三つ形 態があります。遠隔診断では画像診断が主ですが、病院全体で8%程度となっています。 地域にある病院が撮影した画像の判断を離れたところにある大学病院の専門(読影)の医師に見てもらい、アドバイスを受けるケースが多いようです。 第二段階の地域医療圏内の病院間や病院と診療所との連携に際してのITの利用ですが、遠隔診断(画像診断・病理診断)、患者紹介、診療情報の共有の三つ形 態があります。遠隔診断では画像診断が主ですが、病院全体で8%程度となっています。 地域にある病院が撮影した画像の判断を離れたところにある大学病院の専門(読影)の医師に見てもらい、アドバイスを受けるケースが多いようです。

ITを利用して患者紹介を行ったり、診療情報を複数の病院の間で共有したり、交換したりすることも、徐々にではありますが始まっております。

第三段階は全国ベースや生涯に亘る健康・医療情報をITにより管理、活用する段階です。
ところで、国の情報化推進計画として、昨年1月にIT新改革戦略が発表されましたが、戦略の中では、ITは医療の構造改革を実現する手段として期待されております。 そして、
1) レセプトの完全オンライン化による事務経費の削減と予防医療への活用
2) 個人が生涯を通じて健康情報を活用できる基盤づくり
3) 医療情報化インフラの整備、の3つを加速的に進めるべきとしています。

 レセプトは、診療報酬明細書とよばれるもので、病院が診療に要した経費を健康保険組合などに請求する資料で年間16億件、30億枚以上のレセプトが処理さ れていますが、現在は殆どが紙ベースの手作業で行われています。 これを5年度には、銀行で行われている決済のようにオンライン化し、ITを活用して処理する予定です。 手作業の事務に係わる経費が大幅に削減されるだけではなく、レセプトを電子的診療情報として蓄積、分析することにより予防医療へ活用することが可能になり ます。 レセプトは、診療報酬明細書とよばれるもので、病院が診療に要した経費を健康保険組合などに請求する資料で年間16億件、30億枚以上のレセプトが処理さ れていますが、現在は殆どが紙ベースの手作業で行われています。 これを5年度には、銀行で行われている決済のようにオンライン化し、ITを活用して処理する予定です。 手作業の事務に係わる経費が大幅に削減されるだけではなく、レセプトを電子的診療情報として蓄積、分析することにより予防医療へ活用することが可能になり ます。
 2)の生涯を通じた健康情報の活用ですが、これは、国民一人ひとりが、自らの健康状態を正確に把握し、生涯を通じて利活用し、生活習慣などをコントロール することにつなげようとするものです。 日本の医療費の動向を見ますと、医療費の総額は32兆円程度ですが、厚労省ではこれが20年後の2025年には 69兆円になると推計しています。 医療費の大部分は患者の自己負担や国民が支払っている保険料で負担されていますが、約25%、現在では8兆円が国の税金で負担されております。その他に介 護保険の負担が2兆円あり、医療と介護が国の財政の中で大きな比重を占めています。また、1人あたりの医療費を年齢別で見てみますと、20-29歳では年 間8万円程度ですが、70歳以上になりますと64万円(老人医療保険制度で負担比率が減少し5万円)となります。 高齢者はどうしても医療費がかかります。 昨今、少子高齢化が進むにつれ、医療費は毎年1兆円程度ずつ増しており、将来その増大を負担できるかが課題になっております。 2)の生涯を通じた健康情報の活用ですが、これは、国民一人ひとりが、自らの健康状態を正確に把握し、生涯を通じて利活用し、生活習慣などをコントロール することにつなげようとするものです。 日本の医療費の動向を見ますと、医療費の総額は32兆円程度ですが、厚労省ではこれが20年後の2025年には 69兆円になると推計しています。 医療費の大部分は患者の自己負担や国民が支払っている保険料で負担されていますが、約25%、現在では8兆円が国の税金で負担されております。その他に介 護保険の負担が2兆円あり、医療と介護が国の財政の中で大きな比重を占めています。また、1人あたりの医療費を年齢別で見てみますと、20-29歳では年 間8万円程度ですが、70歳以上になりますと64万円(老人医療保険制度で負担比率が減少し5万円)となります。 高齢者はどうしても医療費がかかります。 昨今、少子高齢化が進むにつれ、医療費は毎年1兆円程度ずつ増しており、将来その増大を負担できるかが課題になっております。
 国は患者の負担率のアップや診療報酬の体系の見直し行い、また、高齢者医療制度の導入を検討していますが、中長期的には健康づくり・疾病予防が医療費の増 加抑制に一番効果があります。 肥満、糖尿、高血圧、高脂血、これらの生活習慣病の予防を徹底させないことには患者の負担をいくら上げても医療費は減らな いということです。 生活習慣病の予防徹底により患者数が減少したり、あるいは重症化を防ぐことできるなどにより、2025年度で6兆円の給付費削減が可能になるといわれてい ます。 生涯を通じた健康情報の活用は、健診・検査情報、診療情報、あるいは食事や運動の情報・記録を蓄積・活用することにより疾病の予防に役立てること 目的にしております。 国は患者の負担率のアップや診療報酬の体系の見直し行い、また、高齢者医療制度の導入を検討していますが、中長期的には健康づくり・疾病予防が医療費の増 加抑制に一番効果があります。 肥満、糖尿、高血圧、高脂血、これらの生活習慣病の予防を徹底させないことには患者の負担をいくら上げても医療費は減らな いということです。 生活習慣病の予防徹底により患者数が減少したり、あるいは重症化を防ぐことできるなどにより、2025年度で6兆円の給付費削減が可能になるといわれてい ます。 生涯を通じた健康情報の活用は、健診・検査情報、診療情報、あるいは食事や運動の情報・記録を蓄積・活用することにより疾病の予防に役立てること 目的にしております。
 終わりに、生活習慣病の発症予防や重症化予防では、国民一人一人が自ら管理する情報に基づき、健康の増進に努めること、加えて、地域や職域での健康づくり や国や地方自治体による保健事業が協力しながらそれを支援していくことが必要です。 皆様方も、是非、健康情報を常に把握し、生活者としてのアクティビティを高め、健康な生活を送っていただき、併せて医療費の伸びの抑制にも貢献していただ ければと思います。 ご清聴有難う御座いました。 終わりに、生活習慣病の発症予防や重症化予防では、国民一人一人が自ら管理する情報に基づき、健康の増進に努めること、加えて、地域や職域での健康づくり や国や地方自治体による保健事業が協力しながらそれを支援していくことが必要です。 皆様方も、是非、健康情報を常に把握し、生活者としてのアクティビティを高め、健康な生活を送っていただき、併せて医療費の伸びの抑制にも貢献していただ ければと思います。 ご清聴有難う御座いました。
【報告者注】今回は、講師から上記の如く詳細な講演録を作成して頂いたので、そのご好意に甘え、原文のまま報告させて頂いた。 |

 さて、医療情報のIT化ですが、進展の段階を大きく分類しますと、
さて、医療情報のIT化ですが、進展の段階を大きく分類しますと、 第二段階の地域医療圏内の病院間や病院と診療所との連携に際してのITの利用ですが、遠隔診断(画像診断・病理診断)、患者紹介、診療情報の共有の三つ形 態があります。遠隔診断では画像診断が主ですが、病院全体で8%程度となっています。 地域にある病院が撮影した画像の判断を離れたところにある大学病院の専門(読影)の医師に見てもらい、アドバイスを受けるケースが多いようです。
第二段階の地域医療圏内の病院間や病院と診療所との連携に際してのITの利用ですが、遠隔診断(画像診断・病理診断)、患者紹介、診療情報の共有の三つ形 態があります。遠隔診断では画像診断が主ですが、病院全体で8%程度となっています。 地域にある病院が撮影した画像の判断を離れたところにある大学病院の専門(読影)の医師に見てもらい、アドバイスを受けるケースが多いようです。


 レセプトは、診療報酬明細書とよばれるもので、病院が診療に要した経費を健康保険組合などに請求する資料で年間16億件、30億枚以上のレセプトが処理さ れていますが、現在は殆どが紙ベースの手作業で行われています。 これを5年度には、銀行で行われている決済のようにオンライン化し、ITを活用して処理する予定です。 手作業の事務に係わる経費が大幅に削減されるだけではなく、レセプトを電子的診療情報として蓄積、分析することにより予防医療へ活用することが可能になり ます。
レセプトは、診療報酬明細書とよばれるもので、病院が診療に要した経費を健康保険組合などに請求する資料で年間16億件、30億枚以上のレセプトが処理さ れていますが、現在は殆どが紙ベースの手作業で行われています。 これを5年度には、銀行で行われている決済のようにオンライン化し、ITを活用して処理する予定です。 手作業の事務に係わる経費が大幅に削減されるだけではなく、レセプトを電子的診療情報として蓄積、分析することにより予防医療へ活用することが可能になり ます。 2)の生涯を通じた健康情報の活用ですが、これは、国民一人ひとりが、自らの健康状態を正確に把握し、生涯を通じて利活用し、生活習慣などをコントロール することにつなげようとするものです。 日本の医療費の動向を見ますと、医療費の総額は32兆円程度ですが、厚労省ではこれが20年後の2025年には 69兆円になると推計しています。 医療費の大部分は患者の自己負担や国民が支払っている保険料で負担されていますが、約25%、現在では8兆円が国の税金で負担されております。その他に介 護保険の負担が2兆円あり、医療と介護が国の財政の中で大きな比重を占めています。また、1人あたりの医療費を年齢別で見てみますと、20-29歳では年 間8万円程度ですが、70歳以上になりますと64万円(老人医療保険制度で負担比率が減少し5万円)となります。 高齢者はどうしても医療費がかかります。 昨今、少子高齢化が進むにつれ、医療費は毎年1兆円程度ずつ増しており、将来その増大を負担できるかが課題になっております。
2)の生涯を通じた健康情報の活用ですが、これは、国民一人ひとりが、自らの健康状態を正確に把握し、生涯を通じて利活用し、生活習慣などをコントロール することにつなげようとするものです。 日本の医療費の動向を見ますと、医療費の総額は32兆円程度ですが、厚労省ではこれが20年後の2025年には 69兆円になると推計しています。 医療費の大部分は患者の自己負担や国民が支払っている保険料で負担されていますが、約25%、現在では8兆円が国の税金で負担されております。その他に介 護保険の負担が2兆円あり、医療と介護が国の財政の中で大きな比重を占めています。また、1人あたりの医療費を年齢別で見てみますと、20-29歳では年 間8万円程度ですが、70歳以上になりますと64万円(老人医療保険制度で負担比率が減少し5万円)となります。 高齢者はどうしても医療費がかかります。 昨今、少子高齢化が進むにつれ、医療費は毎年1兆円程度ずつ増しており、将来その増大を負担できるかが課題になっております。 国は患者の負担率のアップや診療報酬の体系の見直し行い、また、高齢者医療制度の導入を検討していますが、中長期的には健康づくり・疾病予防が医療費の増 加抑制に一番効果があります。 肥満、糖尿、高血圧、高脂血、これらの生活習慣病の予防を徹底させないことには患者の負担をいくら上げても医療費は減らな いということです。 生活習慣病の予防徹底により患者数が減少したり、あるいは重症化を防ぐことできるなどにより、2025年度で6兆円の給付費削減が可能になるといわれてい ます。 生涯を通じた健康情報の活用は、健診・検査情報、診療情報、あるいは食事や運動の情報・記録を蓄積・活用することにより疾病の予防に役立てること 目的にしております。
国は患者の負担率のアップや診療報酬の体系の見直し行い、また、高齢者医療制度の導入を検討していますが、中長期的には健康づくり・疾病予防が医療費の増 加抑制に一番効果があります。 肥満、糖尿、高血圧、高脂血、これらの生活習慣病の予防を徹底させないことには患者の負担をいくら上げても医療費は減らな いということです。 生活習慣病の予防徹底により患者数が減少したり、あるいは重症化を防ぐことできるなどにより、2025年度で6兆円の給付費削減が可能になるといわれてい ます。 生涯を通じた健康情報の活用は、健診・検査情報、診療情報、あるいは食事や運動の情報・記録を蓄積・活用することにより疾病の予防に役立てること 目的にしております。 終わりに、生活習慣病の発症予防や重症化予防では、国民一人一人が自ら管理する情報に基づき、健康の増進に努めること、加えて、地域や職域での健康づくり や国や地方自治体による保健事業が協力しながらそれを支援していくことが必要です。 皆様方も、是非、健康情報を常に把握し、生活者としてのアクティビティを高め、健康な生活を送っていただき、併せて医療費の伸びの抑制にも貢献していただ ければと思います。 ご清聴有難う御座いました。
終わりに、生活習慣病の発症予防や重症化予防では、国民一人一人が自ら管理する情報に基づき、健康の増進に努めること、加えて、地域や職域での健康づくり や国や地方自治体による保健事業が協力しながらそれを支援していくことが必要です。 皆様方も、是非、健康情報を常に把握し、生活者としてのアクティビティを高め、健康な生活を送っていただき、併せて医療費の伸びの抑制にも貢献していただ ければと思います。 ご清聴有難う御座いました。