 六稜会報Online No.31(1997.9.15)
六稜会報Online No.31(1997.9.15)●想い出の風景
わが校舎わがグランド(2)
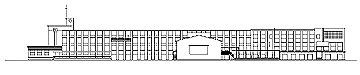
山田文一(60期)
終戦、敗戦−表現はどうでもよかった。昭和20年8月15日、この日から私達の本当の青春が始まった。14歳だった。校舎はかろうじて戦災に遭わずにすんだが、校庭は食糧のための畑のまま、体育館にあった鉄棒も供出されたのだろうか、行方不明のままだった。
一寸拝借のつもりがいつのまにか我が物になって、その鉄棒は多分、体育館が焼けるまで、大勢の若者たちに愛され続けたに違いない。何もない廃墟の中から立ち上がった私達の心の支えでもあった鉄棒、青春の思い出が一杯つまっていた鉄棒。
おかげで、私は第1回国体の器械体操の鉄棒規定で1位となった、あの鉄棒の鬼、小野喬氏をおさえて。何年か後、逆車輪を廻っていて、その鉄棒から飛んでしまい、1ヵ月は首が廻らなかった。その時痛めた頚椎損傷のため、いまもマッサージが欠かせないが、マッサージのたびにあの鉄棒を思い出す。(写真=今はなき旧体育館の屋根の上で)
大谷昌平(69期)
3年間の高校生活を終えて、大学への合格はおぼつかないと先生に指摘されていても自分では合格するつもりで受験して、やはり落ちたという人はかなりいた。受験に失敗した同級生は、東京や京都や地元大阪の予備校へと散らばっていったが、当時は予備校の数も少なく、もう一つの道として北野の中に補習科というのがあった。
現役生の時間割で体育などで空になる教室を転々としながら、その時間に手の空いた先生が普段の授業と変わりなく教えてくださるシステムで、1クラスか2クラスあったように思う。このクラスでは現役時代の3年間には、一度も一緒にならなかった人が1つのクラスにまとまったこともあって、また受験という同じ目標に向かっていたこと、一方現役時代の校則にしばられない自由さを満喫できたことなどによって、不思議な連帯感ができて楽しい一年間を過ごした。
体育の時間はなかったが、こづかいを出し合ってソフトボールとバットを買い、ソフトボールをやったり、大手前高校出身の浪人と対抗試合をしたり、現役学生がやっていたようなことは何でもやっていた。当時の受験生活には偏差値という言葉もなく、北野の模擬試験で何番というのが志望校決定の目安になっていたので、模擬試験の時は予備校に通っていた人も受験しに来ていたように思う。
大学を卒業し、社会人になっても、この時の連帯感はいまでも残っており、人生における大きな支えになっていることは確かである。
梶本興亜(73期)
「化学研究部」に青春の想い出を重ねる人は多い。化学という学問の持つダイナミックな性格に憧れを感じて入部した人たちもまた、ダイナミックであった。
化学研究部は昭和24年に、それまでの理科研究会から独立して誕生したと伝えられる。その時に、地学部、物研等もできたらしい。昭和40年頃までに『試験管』という機関誌が2度ほど発刊されたが、ともに数巻の継続で終わっているようである。私は昭和33年から36年まで化研に所属したが、その間に2度目の『試験管創刊号』を部員たちで発刊した。創刊号には京都大学工学部長であった曽我直弘教授(28年卒、当時は助手であった)の特別寄稿があり、諸先輩方からの励ましの言葉がある。ここでは、そのダイナミックさの一端をまず稲森芳博氏(29年卒)と小池浩氏(30年卒)の文章をお借りして紹介しよう。
----------化研部の機関誌を発行される由、ご苦労さんです。そもそも化研とは、北野高等学校化学研究部の略で今までに世にも珍しき逸材を世に出しております。山本さん、小島豊さん(27年卒)をはじめとして、吉川竹四郎さん(昭和30年卒、Osaka Contract Bridge Clubの創始者)、山形圭三さん(31年)、壇須寿雄さん(32年)、菅正徳(32年卒、名応援団長)、藤原俊一(33年卒、自称爆弾男。化研特製爆弾で全治20日間の傷を負った)等。
----------私たちが化研部員だった頃は最もたちの悪いのばかりが寄っていたように思われる。先輩たちに比して最も活躍したようでもあるが、いたずらをやったことも甚だしく、金森先生等随分我々の存在が迷惑になったことと思う。
こういった先輩方の活躍の結果として、我々の時代には「化研の部室」が無くなっていたのではないかと上記の文章を読みながらハタと気付いた。
さて、このような時代を経て、昭和30年代の高度成長期には化学は技術発展の先導役であった。これを反映して化学の人気は高く、部員の数も増加し、35年度生は16名、36年度生は13名を数えた。荒々しい伝統の化研部にも女性部員が増加したが、イタズラ学は絶えることなく、文化祭の前夜には合成酒が準備され、教員宿直室の前で爆発が起った。 もちろんマトモな研究の方にも力が入り、34年度には「金属イオン全定性分析」、35年度には「淀川への海水の遡上の研究」(水中の塩素イオン濃度の経時変化の測定)、さらに36年度には当時の公害調査の先駆けである「淀川の水質検査」も手がけられた。一方で、化研からのキャンプやハイキングもあり、淡い青春のときめきの場面もあった。化学研究部は受験勉強が大きなウエートを占める高校後半の生活の中で「オアシス」であり「もう一つの教室」であったという事が出来る。
壽榮松正信(74期)
子供、特に男の子は手に入らないものに夢を持つものである。この望遠鏡が健在だった頃の子供は、月にウサギが居るとは思わなかっただろうが、火星の生物の存在には興味があったものだ。20年前のヴァイキング1号・2号、先日のマーズパスファインダーでその夢も壊されてしまったが。
望遠鏡については、石川勇さんを忘れるわけにはいかない。71期の石川さんは在学中47cmの主鏡(凹面鏡)から手作りで作り上げ、当時府内でかなり話題になった。昨今の既製品万能の時代では考えられない努力が必要で、2枚のガラスを何十万回も摺り合わさなければならない。この望遠鏡は今も能勢の野外活動センターで、夢多き子供たちに貴重な経験の場を提供している。
屋上の望遠鏡が健在であった頃、地学部員が中心になって観測会を催した。月食や日食、教科書でしか見られなかった月のクレーターや土星の輪など、空気の状態によって起こる揺れも含めて、ゆらゆらと動いて見えることの感動を今も持ち続けている方も多いことだろう。地上の風物を見て(天体望遠鏡は上下逆さに見える)「スカートはどうなるのかな」という不届きな人もいたが。
いま、石川さんを中心に望遠鏡の再建の話も持ち上がっている。十三のような明るいところでは、星雲などの暗いものは見えないだろうが、太陽、月、惑星、それに近頃よく話題になる彗星などは観測の対象に充分なりうる。そのうえ、現在の技術ではCCDカメラなどを用いて、多人数の子供たちに見せることも可能である。このような都会の真ん中で、手軽に観測できる絶好の場所に設置する意味は大きいと思わる。校舎改築の折り、ぜひとも屋上にドーム付きの望遠鏡をと頑張っておられる。
岡村隆久(77期)
私が北野の美術部で指導を受けたのは岡島吉郎先生だった。私が卒業して2、3年で退職されたが、ほぼ40年間北野一本でやってこられた名物先生である。
私のいた頃は岡島先生の教職生活最晩年で、こわいというより穏やかな印象が強かったが、先輩達には、こわいこわい先生だったとよく聞かされた。北野出身の若い先生が顔をしかめて岡島先生のことをぼやいておられたのが思い出される。その若い先生も今や好々爺である。
美術準備室を二分して奥の窓のある方が先生の部屋、廊下側が部室だった。部室でのあほなおしゃべりを先生は皆聞いておられたはずだが、そのことを口に出されたことは一度もなかった。
具体美術の運動は、後年「グタイ」として先駆的活動が国際的にも高い関心を呼ぶようになった。美術の世界のそれまでの常識が崩れていった。美術混沌時代の始まり。そんな時代、我々も絵の具の代わりに紙や木を貼りつけたり、少し焦げめをつけてみたり…。流れに取り残されまいと、混沌と戦っていたのかもしれない。
毎年夏休み、我々美術部員は志摩半島の波切という村に連れて行ってもらった。日照りの中、坂や階段の多い漁村を上へ下へと汗だくになって歩いてたくさんの絵を描いた。今、その頃の絵が出てくれば感動ものなんだが…。民宿のようなところに泊まり、自由に散策し、灯台を見て、太平洋を見て、魚を食って、何から何まで新鮮で感動的だった。日頃の油くさい美術教室や部室からの解放感も加わって、素晴らしい思い出となっている。
当時軟弱イメージの美術部に、五人の同学年男性がいた。上や下の学年は、ほとんどが女性で、そんな仲間達とは今でも会えば楽しい。
 鉄棒の思い出
鉄棒の思い出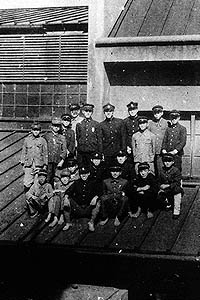 昭和21年の秋、第一回国体が大阪で開催されることとなった。器械体操の種目は今のように6種目ではなく、鉄棒、跳箱(今の跳馬のこと)、徒手体操(今の床)の3種目。跳箱と徒手は何とかできる、しかし鉄棒はどうにもならなかった。器械がなければ練習もできない。国体出場も諦めねばならないか、と思っていたとき、思わぬ助っ人が現われた。55期の藤井博氏である。氏は当時在学中の関西大に使ってない鉄棒があるからと言ってくださったので、同期の吉田、61期の仙波などと取りに行った。
昭和21年の秋、第一回国体が大阪で開催されることとなった。器械体操の種目は今のように6種目ではなく、鉄棒、跳箱(今の跳馬のこと)、徒手体操(今の床)の3種目。跳箱と徒手は何とかできる、しかし鉄棒はどうにもならなかった。器械がなければ練習もできない。国体出場も諦めねばならないか、と思っていたとき、思わぬ助っ人が現われた。55期の藤井博氏である。氏は当時在学中の関西大に使ってない鉄棒があるからと言ってくださったので、同期の吉田、61期の仙波などと取りに行った。
 いつの頃からか補習科があった
いつの頃からか補習科があった
 化学研究部の青春
化学研究部の青春
化研出身者は全く一癖もふた癖もある強者ですが、これらの人達は化研に入る前は「まとも」だったのです。有毒なガスの充満する部屋での3年間、ある時は化研特製の合成酒「化研正宗」の粟井先生、西田先生、北原先生などへの人体に及ぼす反応試験。また、ある時は火薬を作り日頃のうっぷんを晴らしたものです。これでは、まともな人間も変わるのは当然です。
化研特製の煙幕を放り込み校長を煙に巻くような化研部員が出てほしいものです。……こういうことはあまり実行するなよ。----------(稲森氏)
同窓会で北野に参ったとき、拝見すると今日は部室がないようですが、我々の頃は化学教室の約3分の1が我々の部屋に当てられていた。そこに質の悪いのがたむろして雑学研究会を構成していたのである。
雑学中忘れもしないのはイタズラ学。その内容は、サツマノカミ(枕詞)タダノリ学、キセル学、食器蒐集学(食堂の食器が部室に10余個あった)、清酒合成学(エタノール希釈学)。……大学に入ってからこの単位は取らなかった。
イタズラもよくやったがホンマに勉強もよくした。数学、物理学、化学、英語などの難問は絶えず我々の間に発生し、我々の文殊の知恵で解かれた。そういった事が我々高校生の最大関心事である大学入試に期せずも糧となったらしい。
一方、化学研究会としての活躍は、今から考えると随分非理論的であったが、我々が3年の時は、種々のメッキ、銅メッキによる絵画的描写、ポリエステル樹脂の重合、加工、尿素樹脂ベークライト樹脂の重合など随分多岐に渡っていた。従って予算においても、野球部が運動部の横綱である如く化研が最も大きかった。----------(小池氏)
 地学研究部
地学研究部 地学研究部を語る上で、正面屋上に鎮座していた大望遠鏡をはずすわけにはいかない。口径30cm、京都西村製作所で作られたもので、当時も今でも日本の高校では最高レベルのものであった。戦後まもなく先輩有志の寄贈で、昭和27年8月20日に搬入組み立てられた。集光力は肉眼の2500倍もある。昭和も終わる頃、鏡筒部だけでも活かそうと望遠鏡再建を願って解体されたという。現在は台座のみ元の場所に(写真)、本体は屋上の旧部室で静かに眠っている。北野のシンボル「北中」の透彫りの真下である。
地学研究部を語る上で、正面屋上に鎮座していた大望遠鏡をはずすわけにはいかない。口径30cm、京都西村製作所で作られたもので、当時も今でも日本の高校では最高レベルのものであった。戦後まもなく先輩有志の寄贈で、昭和27年8月20日に搬入組み立てられた。集光力は肉眼の2500倍もある。昭和も終わる頃、鏡筒部だけでも活かそうと望遠鏡再建を願って解体されたという。現在は台座のみ元の場所に(写真)、本体は屋上の旧部室で静かに眠っている。北野のシンボル「北中」の透彫りの真下である。
 美術部のこと
美術部のこと 先輩に吉原治良(36期)という画家がおられる。吉原製油の社長でもあった。当時、大阪では具体美術の運動が盛んだった。その中心が吉原治良で、北野では同時代の佐伯祐三の名声に隠れて知名度は低いが、現代美術の世界では今も語られる人である。その吉原さんの描いたあやとりをする少女の絵が、当時は美術教室に掛けてあった。思い出の中では大きな絵だが、実はそう大きくもないことを、120周年記念「六稜会展」で再会して知った。(写真=吉原治良「あやとり」)
先輩に吉原治良(36期)という画家がおられる。吉原製油の社長でもあった。当時、大阪では具体美術の運動が盛んだった。その中心が吉原治良で、北野では同時代の佐伯祐三の名声に隠れて知名度は低いが、現代美術の世界では今も語られる人である。その吉原さんの描いたあやとりをする少女の絵が、当時は美術教室に掛けてあった。思い出の中では大きな絵だが、実はそう大きくもないことを、120周年記念「六稜会展」で再会して知った。(写真=吉原治良「あやとり」)
原典●『六稜會報』No.31 pp.8-13
 北野生の一人として、私もPと呼んで親しんだ本館校舎(写真)が解体されるということには、そこで実際に生活した年月に比してあまりに深い郷愁を覚える。しかし、自分の体験からいえば、本当に一刻も早く、一人でも多くの後輩たちによい環境で北野での生活を送ってもらうことを望むならば、その郷愁は自分の胸の中だけで生きていればよいと考えるようになった。
北野生の一人として、私もPと呼んで親しんだ本館校舎(写真)が解体されるということには、そこで実際に生活した年月に比してあまりに深い郷愁を覚える。しかし、自分の体験からいえば、本当に一刻も早く、一人でも多くの後輩たちによい環境で北野での生活を送ってもらうことを望むならば、その郷愁は自分の胸の中だけで生きていればよいと考えるようになった。