 六稜会報Online No.30(1996.9.15)
六稜会報Online No.30(1996.9.15)●想い出の風景
わが校舎わがグランド(1)
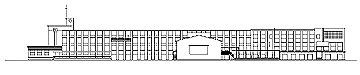
 十三校舎新築のころ
十三校舎新築のころ森島重勝(45期)
45期生は、十三校舎の最初の五年生、つまりは現校舎の第一回の卒業生である。その校舎も早60余年を経て、建て替えとは…。私ども45期生の手で、第一の爆破のスイッチを押してみたい気もする。
昭和6年(1931)3月末、全校生徒は手に手に、博物標本、地図など小物類をさげ、大八車に机椅子を積み、長い行列を連ね、ガタガタ揺れるボロ十三橋を渡り、たもとの「十三やきもち」をほおばり、引越しを手伝う。
芝田の校舎は明治35年(1902)建設のしろものだけに、床板も腰板も継ぎはぎだらけだった。そんな校舎で4年間暮らした私どもには、十三の新校舎は見るものすべてが新品、しかもその華麗さに目をみはるばかり。
第一に度胆を抜かれたのが講堂だった。正面の壇上の立派なこと。上を見ればシャンデリア。それに広いこと。「これなら全校生徒みな入るでえ」と感嘆。その筈、4年間の芝田校舎では全校生が一堂に会しての式があった記憶がないのだ。校舎の外壁がクリーム色のタイル張り、全校内にスチーム暖房がついているときた。3階教室は明るく、外に目をやれば淀川の堤防、対岸には梅田のビル、阪急電車の鉄橋が見え、日当たりがよく暖房もきいていて、のせている弁当のお菜のほのかな香りに、こっくり組が頻発する。
同級生塩浜文雄君がうたう。「北大阪線からは、剣道場の破れガラスがよくみえた。一日雨が降れば、二、三日朝礼なしの運動場。式は二部に分かれての講堂、しまいには講堂の中に教室もできた。狭くて、夏は汗臭く、冬は寒風入り。唯一のストーブに全先生が集まる職員室。今度はうちの学校、鉄筋だぞ。クリーム色のビルディング。ボロからのがれた我々に『きたの! きたの!』と淀川が迎えてくれた。うれしいな。」
11月に落成式がある。校友会誌『六稜』第74号はその記念誌とするので投稿大募集と発表された。我こそはと大勢の少年文士が名乗りをあげた。しかし、この落成式は、校内チブス事件のため延期となり、我々が去ったあとの4月に挙行された。
記念式の歌の歌詞は5年生塩浜文雄君が当選、佳作に同じ仲間の5年生、後の大文士 野間宏君のが入る。
野間君の作品をご紹介しよう。
水にときわのしるき 淀川べりにそそり立つ
若きほこりの殿堂は 今こそ成れり 今ぞ成る
山にみどりの影仰ぐ 学びの園は風光り
百花匂ふ常春ぞ 祝へ祝はん今日の日を
また彼は「野間令一郎」のペンネームで、「落成式 俳句で祝ふ」と二十数句を発表している。その内の五句を記す。
落成式 黄金造りの 太刀はかん
鳳凰の 飛び来るらん 落成式
あらたふと 北野を包む 紫雲かな
祝ひせん おくりものせん 雁の涙を
落成や 身は幽遠の楽土かな
原典●『六稜會報』No.30 p.8