 六稜会報Online No.29(1995.9.15)
六稜会報Online No.29(1995.9.15)●1994年総会卓話抄録
北野 NEXT CENTURY PROJECT
京都大学工学部建築学科助教授
竹山 聖(85期)
-
私は昭和45年に入学しました。入学式の半月程前に大阪万博が開幕しまして、高度成長の最後のはなやかな時代を高校で送り、調子に乗って建築学科を選び、京都大学の1回生の秋にオイルショックに見舞われ、卒業の時は理科系の学生はまったく就職がないという状態でした。今、教えている学生は大体70年代生まれで、そういう話がすでにわからなくなっています。歴史とか記憶とか、そういうものの継承はどういうふうに行なわれていくのだろう。そんなことを考えながら、今回の校舎の計画に当たっています。
現在の校舎は、1930年に着工して31年に完成しました。建築は滅び方が非常にゆっくりなので、それと気がつきません。ここ3年ほど、校舎の耐震診断が行なわれ、その結果、構造的に危ないという結果が出たようです。それに、大阪府のプログラムで、古いナンバースクールは建て替えの時期だということで、他の伝統校はほとんど改築を終えています。北野も、そういうことで改築をすることになったわけです(プール・体育館・第2新館は残しますから改築といいます)。
府立高校ですから、大阪府がオーナー、府の教育委員会がクライアント、府の営繕部が設計者、北野の教職員・生徒は単なるテナントである、という位置付けになるのです。ここに問題となってくるのは、平等化、画一化ということです。現在の府立高校の基準通りに、ごく一般的な、豆腐を切って並べたような高校の設計で建てて、果たして北野高校はそれでいいのか。120年の伝統のある北野高校で、単なるテナント扱いもないやろう。そう感じまして、営繕部から発注を受けて仕事を進めていた高橋上田設計事務所の高橋さん、大谷さん(どちらも北野の先輩)、前校長の足立先生、肥塚教頭とお話をして、新しい案を提示させてもらいました。幸い、双方にいい感触をもっていただいたというわけです。
では、何が記憶の継承であり、北野の伝統であると考えられるのか。北野では、僕も入学してすぐに思ったわけですけれども、画一的あるいは平均的な教育とは全く逆の教育がなされてきたのではないかと思います。先生方が個性豊かで、それぞれの先生の関心のあるフィールドを自由にお話されていたようですし、生徒の方も、聞くも自由聞かぬも自由といった雰囲気があった。自由は責任を伴いますが、主体的に学ぶなら学ぶ、運動するなら運動する、遊ぶなら遊ぶということが行なわれていたと思います。そのような精神をうまく学校の建築に反映できないかと、まず考えました。
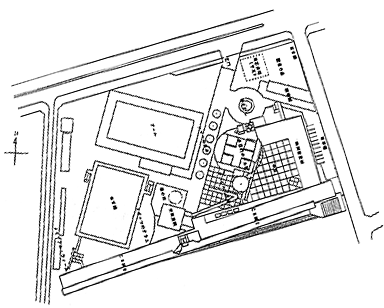
-
今回、三つの柱を掲げました。まず一つ目は自由と主体性、二つ目は古いものと新しいものの共存、三つ目は余白の形成です。今回の設計案では、この北野高校に来た人が各々の目的に応じて自由にアプローチできるようになっています。先生方、生徒、来客それぞれが、さまざまな道筋を通ってさまざまな場所にアプローチできる、どこも皆違うというような空間を作っております。これはある意味では現在の校舎の特徴でもあります。全体としてのアイデンティティーがありながら、それぞれ光や空気の異なる空間を生徒や先生が自由に使いこなしています。それを発展させて、この精神面での歴史・伝統を継承できるのではないかと考えました。
次に、現在の校舎の記憶をうまく受け継ぎたいと思いました。今の校舎の味わいは、長い空間なのではないでしょうか。長い廊下の空間と中庭を持つ空間が一体化された校舎、このPの字型というのが異なった場所を生み出すのに非常にいい形態なのですね。設計案では、現在のPの字を反転して置いたような形で全体の計画が作られています。現在のテニスコート辺りに新校舎の基本的な部分が来ます。こうしますと長い空間が南向きになりまして、校舎の南側にグラウンドが来るという理想的な形になります。それに、現在の校舎を残したまま、建設がすすめられ、引越しがすんでから古い校舎を壊していくことができます。
バックネット裏に大きな楠がありますが、これを残して「楠の広場」とします。ここが、生徒の入口、多目的ホールへの入口になり、楠が新しい校舎になっても生徒たちを見守っていく。こうして、一つの記憶の継承が図られ、機能を超えた象徴的なレベルでの伝統の継承が行なわれるのではないかと考えました。
「楠の広場」は体育館やプールと同じ向きを持ちます。メインアプローチもその軸を踏襲します。講堂に代わる多目的ホールもプール中央の軸線上にのります。古い秩序を継承して新しい秩序に移していくというわけです。
また、現在の校舎に残る弾痕の跡を保存して、メモリアルウォールとします。
北野には教育史上貴重な資料が多く所蔵されていると聞きます。これを守り展示するためには、府の基準を超えた大きな図書館、あるいは併設した資料館、同窓会館というものが必要でしょう。
伝統あるいは記憶をしっかり継承するという精神を持って、新しいものを育てるということが本当の意味で伝統を守ることになるのではないでしょうか。
ネクストセンチュリーと言いましたのは、百年もつ建築を考えるという意気込みを表わしています。現在の校舎が昭和の名学校建築であるならば、平成の名学校建築を目指すという意気込みも表わしています。そうした校舎に向けて、同窓会の皆さんの全面的なバックアップをお願いしたいと思います。
原典●『六稜會報』No.29 p.3