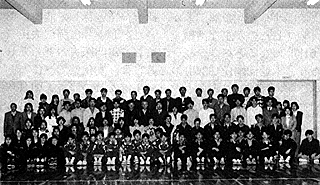 【特集】六稜クラブ活動小史
【特集】六稜クラブ活動小史卓球部
六稜杯争奪戦、年2回開催
「卓球便」で結ぶOBと現役
【写真】'93年3月27日の六稜杯より
-
ほかの多くの部と同様に新制高校がスタートした昭利23年の創部。45年の歴史を持ちながら戦績面で確かに華やかなものはない。が、OB会のまとまりの良さと現役との交流の緊密さは、他の部の追従を許さない、というのが自慢だ。
身近な卓球便
特に、年二回発行する会報は“卓球便”と称し、会員諸兄姉の近況、現役の戦績などが満載、このためOB諸氏にとっては宅急便より身近なものになっている。
昭和63年の『六稜卓球部OB会報』(創部40周年記念号)には「今年も、4月の初めに一通の茶色の事務封筒に入った郵便を受け取った。その封を切らなくても中には一枚のはがき、青い振替用紙、それに上質紙にガリ印刷の『卓球便』が入っていることが分かる。先ず告知の欄を探し当て六稜杯の開催日を確かめるのだ………。」
との投稿があるほどだ。
その六稜杯だが、創部30年を記念して、当時の顧問だった薬師寺春雄先生らの尽力で創設された。趣旨はOBも含めた北野卓球部の親睦をはかるとともに、現役の励みにというもの。毎年春と秋の二回、現役とOBが技を競うのだ。当然のことながら女子の部の優勝者にも六稜杯が授与される。大会後の懇親会は“卓球ファミリー”そのもので、試合より懇親会目当てのOBも多くなったようだという。
球探しにひと苦労
そんな和やかな卓球部だが、卓球便から歴史を拾ってみると、昭和23年の1学期、同好の仲間が集まって始めた。当時は、台すらなく、空き教室の机のうえに板を渡し、にわか卓球台でピンポン球を打ちあうという程度のものだった。床は穴だらけのうえ、窓ガラスはわれ放題だったので得意のスマッシュが決まっても、穴ぼこに入ったのや屋外に飛び出した球探しに練習より神経を使っていたという。
24年には正式に部として発足、予算も付いた。翌年の府大会個人戦で早くもベスト16に斎藤信義氏(63期)が入った。が、練習場こそ旧図書館の2階に確保できたものの床はコンクリートでボコボコ、加えて窓ガラスは破れたままの悲惨なもので、一向に成績は上がらなかった。が専用の練習場とあって、部員は練習に没頭した。
その成果が現れたのが31年から33年にかけての活躍である。とりわけ69期の小林力三氏は、国体出場こそ逃したものの、府予選でベスト4に進出した。その後女子が49年に、大阪府のベスト8になり、京阪神大会への出場や北摂大会の優勝が続いた。最近では平成3年に男子ダブルスで近畿大会に出場したのが光っている。
最後になったが、この部には関東支部があることを付記せずにはいかない。48年に東京周辺に住むOBらで結成、港区の区民大会に「六稜クラブ」の名で出場、団体の二部で2位、個人セミシニアで田中康彦氏(73期)が優勝するなど東京にも「六稜」の名を広めていることだ。
原典●『六稜會報』No.26 p.18