
現場突撃インタビュー(1)
平成11年3月17日
reporter:壽榮松正信(74期)
新校舎建設の現場監督、切石邦彦氏(財団法人大阪府建設監理協会)にお話を伺いました。
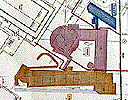      |
-
■現在の工事の状況を教えてください。
今は、基礎のコンクリートが終わり、1階のコンクリートを打つために仮枠を造っているところです。A棟が一番進んでいます。円形の多目的ホールです。次にB棟…事務室や校長室といった管理施設が入る…このL字型の部分ですね。A棟は3月23日、B棟は3月29日にコンクリートを打つ予定です。それぞれ1階部分だけですが。
■コンクリートはすぐに固まるのですか。
硬化は1時間チョットで始まります。今の時期ですと、1週間ほどもすれば「設計強度」まで固まりますね。壁なんかは「解体強度」が得られた時点で型枠をバラしますが、梁とかスラブの下の型枠など…構造的に重要な部位については、28日過ぎになると思います。
■全体の工期からみて今の進捗状況はいかがですか。
ほぼ、工期どおり…計画通りに進んでいます。
■学校という現場環境で特に気を使っておられるようなことはありますか。
現在の工法ですと重機の運転音が一番うるさいくらいで…大きな騒音が出にくいのです。ですから案外、静かに仕事が出来ていると思います。試験や重要な学校行事がある日には、あらかじめ学校サイドと打合わせたうえで、午前の作業と午後の作業をやりくりしたり、時には工事を控えたりすることもあります。もちろん、工期を遅らせるわけにはいきませんので、無理をするときもありますが(笑)。
■天候には左右されますか。
今の時期はとくに影響を受けやすいですね。ほとんどが外の仕事ですし、雨天がいちばん困ります。とりわけ土を触る時期には気を使います。ヘドロ状態の時に急いで作業を進めると、却って乾きが遅くなるのです。
幸い、この工事では掘削の時期に雨が少なかったので助かりました。屋内の仕事になれば、雨は関係なくなります。
■今後の大きな予定は。
C棟(図書館棟)やD棟(教室棟)も一切含めて、コンクリート打ちの作業が終わるのが6月末あたりですね。6月の中頃にはアルミサッシ等の取り付け作業が始まります。 それから屋上の防水…そして順次、屋内の仕上げへと掛かっていきます。ここは、コンクリートの化粧打ちっ放しが多くて仕事が難しいですね。
■というと?
工法上、難しい部分があったりします。サッシの溶接部分など…作業スペースの制約で、かなり狭い箇所があって…作業のしにくいところがあるのです。
■A棟のように円形の建築物は、学校建築としてどうですか。
余り見かけませんね。珍しい建物ではないかと思います。下の階の構造がなくて上壁だけが突出しているところとか…かなり変わった形状になっています。
■歴史の生き証人としての樹木(大木)を残したままの工事というのは。
「枝の先は斬ってもいいが、樹型は変わらないように」という指示がありました。そのため…多目的ホールと本館の渡り廊下の設計変更などもありました。大きな枝振りがどうしても塞いでしまうような格好でしたから。
■この工事はいつまでかかるのでしょうか。
第1期工事の工期は10月20日までとなっています。その後、年内に外溝の工事に入る予定ですが、これは発注がまだになっています。ですから、その先はわからないですね。近頃は開かれた学校ということで、塀も低くなる傾向にありますし、大阪市のほうからも「都市景観」の維持という観点から、そうした指導があります。
Last Update: Mar.18,1999