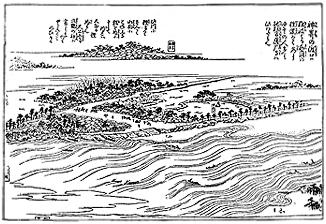 神崎の渡口 『摂津名所図会』 |
神崎の渡
松村 博
(74期・大阪市都市工学情報センター常務理事)
-
『太平記』の記述で、正平17年(1362)に焼き落とされたとされる神崎の橋は、その後の歴史の舞台には登場しません。渡河の必要がなくなった訳ではありませんから、橋の代わりに渡船が設けられていたと思われます。
神崎の渡しの存在は、慶長10年(1605)に画かれた『摂津国絵図』からも読み取ることができます。神崎の渡しを大坂の方から渡りますと、真っすぐに北上して伊丹方面へ至る道と、西行して尼崎へ達する街道に通じており、そこには宿駅が置かれていました。江戸時代の神崎の渡口(わたし)は、『摂津名所図会』によると「昼夜行人絶えず」と表現されるほど、利用者は多かったようです。
神崎の渡しを受け持ったのは兵庫側の神崎村でした。渡しの営業権を与えられ、渡し賃を徴収できるかわりに、幕府の公用である御伝馬御用や大名などの通行に際して、船渡しの御用を勤めなければなりませんでした。
神崎渡しは川幅が300間(約540m)、常水幅は約100m、深さは8尺(約2.4m)でした。明治4年の資料によりますと、渡し賃は1人につき40文で、増水時には6割増しの64文になりました。ただし武士と僧侶は無賃とされていました。渡し船は2艘、他に馬越え船が2艘、平日は5人の船頭が詰めていました。
街道筋に当たる神崎渡しでは、公用の負担が大きく、渡しを担当する村には重荷になり、しばしば御用負担軽減の嘆願がなされました。このためか、中国街道の宿駅にあたる神崎の駅は、伊能忠敬が「何(いず)れの家作宜しからず」と記しているように、施設はかなり貧弱な状態であったようです。
Last Update: Mar.23,1999